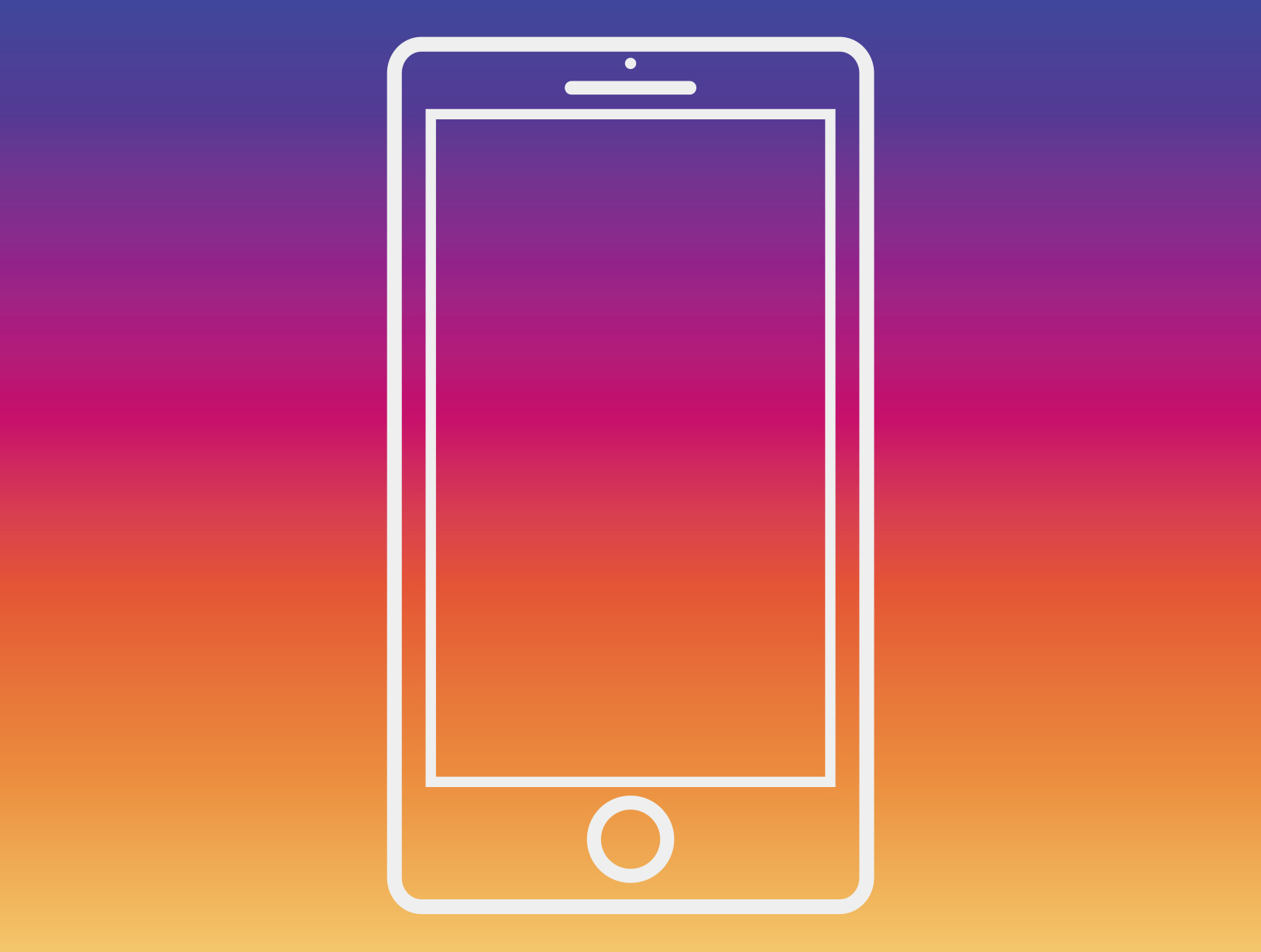Instagramを運用していると、リールを頑張るべきか、それともフィード投稿を丁寧に続けるべきかこの疑問に一度はぶつかるはずです。
結論から言うと、2025年はリール一択というわけではありません。
ただし、目的によってどちらを重視すべきかは明確に分かれています。
この記事では、リールとフィード投稿それぞれの強みを整理し、2025年におすすめの使い分けを解説します。
2025年のInstagramアルゴリズムの大前提
まず押さえておきたいのが、Instagramの基本方針です。
Instagramは今も一貫して新しい出会いを生むコンテンツを優遇するという方向性を強めています。
その中心にあるのがリールです。
一方で、フォロワーとの関係性を深める役割は、今もフィード投稿が担っています。
この役割分担を理解すると、どちらが強いかではなくどう使うかが重要だと分かってきます。
リール投稿が強い理由【拡散・認知】
2025年もリールが強い最大の理由は、フォロワー外へのリーチ力です。
リールは
・発見タブ
・リール専用タブ
・おすすめ表示
を通じて、フォロワー以外にも届きやすい設計になっています。
そのため、
-
フォロワーが少なくても再生される
-
アカウント初期でもチャンスがある
-
バズれば一気に認知が広がる
といったメリットがあります。
特に
新規フォロワーを増やしたい
認知を広げたい
という目的なら、2025年もリールは最優先です。
フィード投稿が今も重要な理由【信頼・定着】
一方で、フィード投稿が弱くなったわけではありません。
むしろ2025年はフィード=アカウントの名刺という役割がより強くなっています。
リールで興味を持ったユーザーは、ほぼ確実にプロフィールとフィードを見ます。
そこで、
-
投稿内容がバラバラ
-
何のアカウントか分からない
-
情報が浅い
となると、フォローされずに終わってしまいます。
フィード投稿はこのアカウントをフォローする価値があるかを判断される場所です。
信頼、専門性、世界観を伝えるなら、フィード投稿は今も不可欠です。
2025年のおすすめ使い分け戦略
結論として、2025年は
リールとフィードの役割分担運用
が最も効率的です。
リールの役割
-
新規ユーザーに見つけてもらう
-
興味を引く
-
アカウントに人を連れてくる
内容は
短く
分かりやすく
一目で価値が伝わる
ことが重要です。
フィード投稿の役割
-
専門性を伝える
-
実績や考え方を見せる
-
フォローする理由を作る
情報整理型の投稿や、保存されやすい内容は、今もフィードが強いです。
実は一番伸びるのはこの組み合わせ
多くの伸びているアカウントがやっているのは、次の流れです。
-
リールで興味を持たせる
-
プロフィールへ誘導
-
フィードで納得させる
-
フォローにつなげる
この導線ができているアカウントほど、フォロワーが安定して増えています。
どちらか一方だけを頑張るより、
リールで集客、フィードで定着
この考え方が2025年の正解に近いです。
じゃあ投稿比率はどうする?
目安としては、
-
リール:全体の6〜7割
-
フィード:全体の3〜4割
このくらいがバランスの取りやすい比率です。
ただし、
商品販売
サービス集客
ブランディング
が目的の場合は、フィード投稿の比重を少し高めても問題ありません。
まとめ
2025年の結論としては、
-
拡散力が強いのはリール
-
信頼を作るのはフィード
-
本当に強いのは両方使えるアカウント
です。
リールかフィードかで迷うより、
役割を分けて設計できているか
を一度見直してみてください。
それだけで、Instagram運用の成果は大きく変わります。